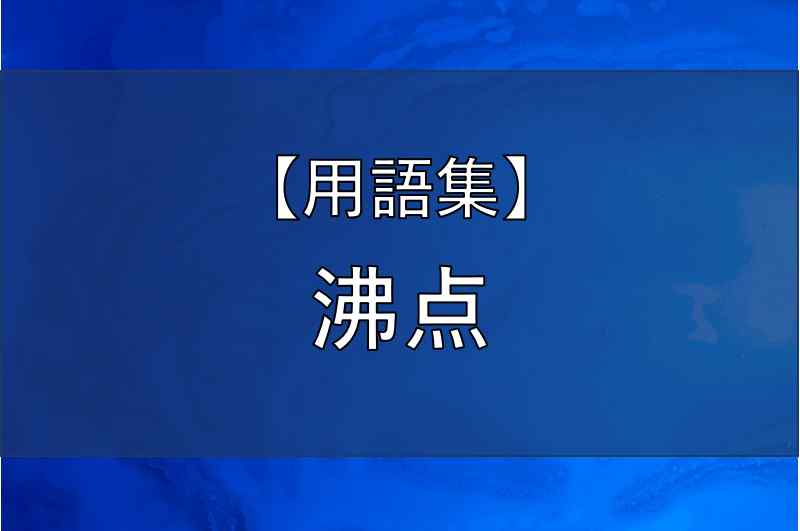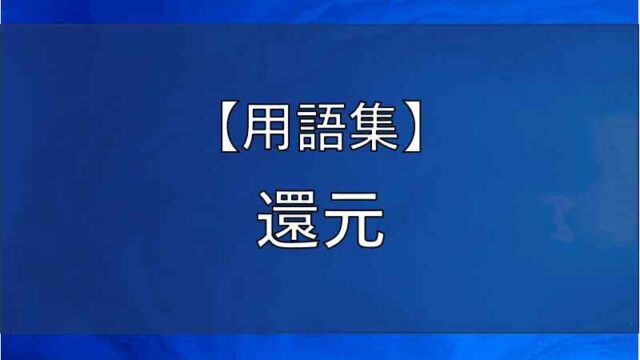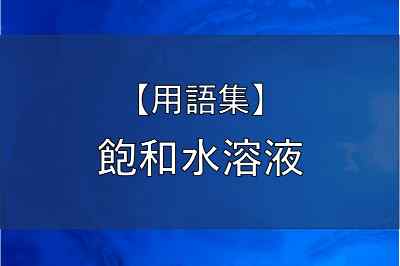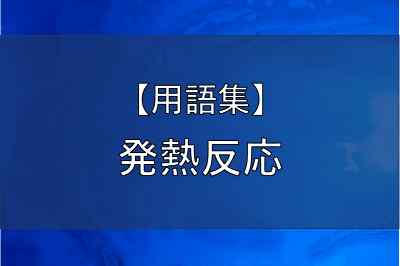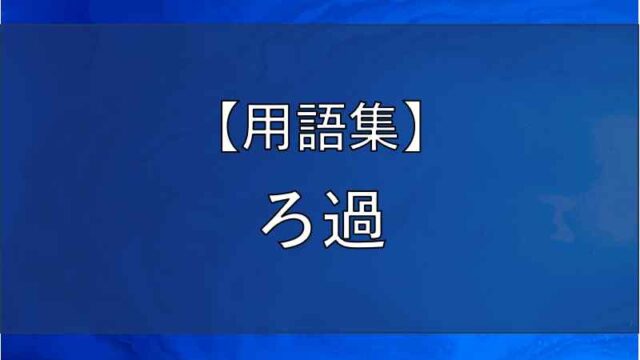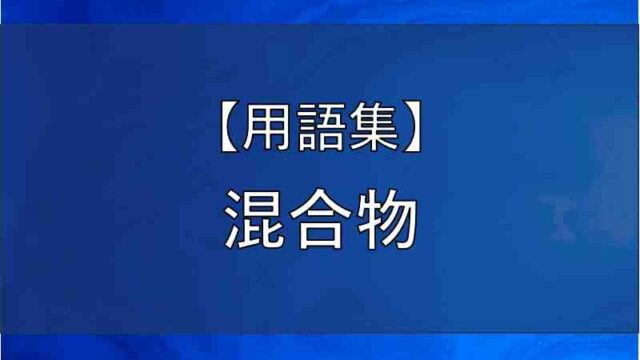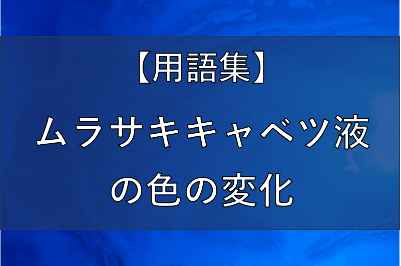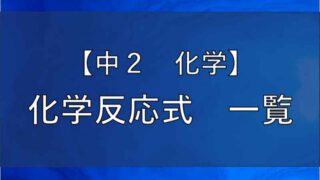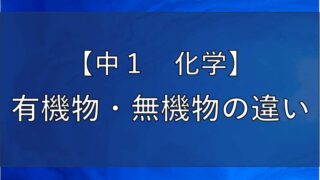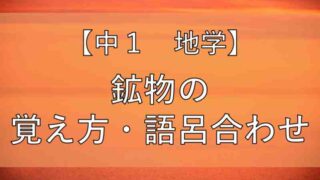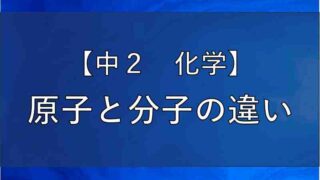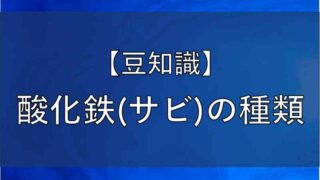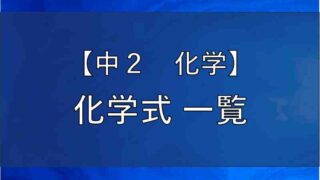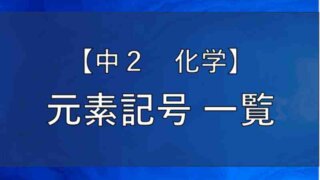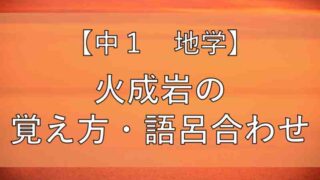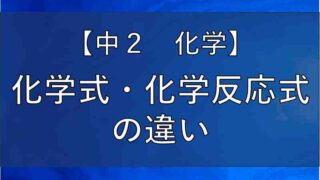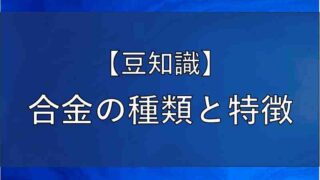中学校の理科では、「沸点」について学習しますが、よく理解できていますか?
この記事では「沸点とは」「色々な物質の沸点」「物質の沸点の例」などについてわかりやすく解説しています。
それでは早速、「沸点」について一緒に学習していきましょう!
1. 沸点とは
「沸点(ふってん)」とは、液体が気体になる温度のことです。
わかりやすい例をあげると、「水」は液体ですが、100℃になると気体である「水蒸気(すいじょうき)」に変化します。
このように液体(水)が気体(水蒸気)に変化する温度を「沸点」といいます。
物質の状態には、「液体」「気体」「固体」の3種類がありますが、「液体」→「気体」に変化する温度だけ沸点を使います。
また、沸点は物質によって違います。
そのため、水とエタノールなど2種類以上の物質が混ざってしまっても沸点の差を利用して物質を分離することができます。これを「蒸留」といいます。
2. 色々な物質の沸点
沸点は、物質によって違います。
ここでは物質の沸点の例をいくつか紹介したいと思います。
下の数値はおおよそのものなので、検索するサイトによって誤差があるかもしれませんが、おおよその値を知っているだけ大丈夫です!
| 水 | 100℃ | 鉄 | 2,862℃ |
| エタノール | 78℃ | 銅 | 2,562℃ |
| 窒素 | -196℃ | パルミチン酸 | 351℃ |
| 酸素 | -183℃ | 金 | 2,700℃ |
| 食塩 | 1,465℃ | タングステン | 5,555℃ |
ちなみに、沸点が最も低い物質は「ヘリウム(He)」で -269℃、沸点が最も高い物質は「タングステン(W)」で 5,555℃ です。
物質によって、沸点は全く違うのが分かりましたでしょうか?
沸点が常温より高いものは普段は「液体」や「固体」で存在しており、沸点が常温より低いものは普段は「気体」で存在しています。
もっとたくさんの物質の融点・沸点について知りたい方は下の記事も参考にしてください!
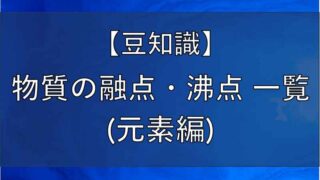
物質の融点・沸点 一覧 【元素編】
物質はその種類ごとに沸点と融点が決まっているのは知っていましたか?
この記事では、「沸点・融点とは」「物質の沸点」「物質の融点」...
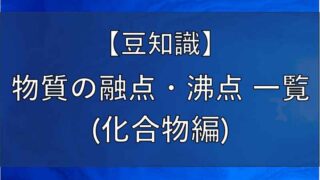
物質の融点・沸点 一覧 【化合物編】
物質には様々な化合物がありますが、化合物の融点・沸点は知っていますか?
この記事では、「融点・沸点とは」「化合物とは」「化合物の...